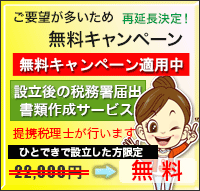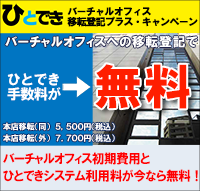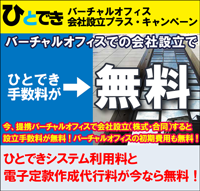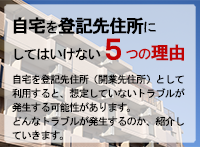消費税の納付税額とは一体どのように計算すればよいのでしょうか?
通常は (課税売上高)×4%-(課税仕入高)×4% このように計算しますが、その他に
簡易課税制度の適用を受けると、また別の計算方法になります。
その場合は課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が5千万円(注)以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出していることが条件になります。
消費税の節税に関しては、会社設立後の届出の選択により方法が異なります。
ひとつは、設立時の資本金を1000万円未満にして、「消費税免税事業者」とするか?
資本金の額に拘わらず、「消費税課税事業者」を選択するという方法があります。
消費税の免税業者については、前回でもお伝えしました。
では、「課税事業者」というのはどういったことなのでしょうか?
その最大のメリットとしては、還付を受けられるということです。
何が還付されるかというと、受け取った消費税より支払った消費税が多い場合に戻される差額です。
消費税の免税関しては、新設の会社の売上高がどのくらい見込めるか?を慎重に判断することが大切です。
事業年度開始の日の資本の金額が1,000万円未満であれば、会社設立後の届出で免税事業者になれます。
確かに、免税事業者になれば最低2期分は納税義務が生じないので、消費税が節約できると考えるのも無理はありません。
しかし、免税期間と事業年度、売上高による「免税事業者か?課税事業者か?」の選択によって、消費税の納税に少なからず影響が出ます。
 消費税は流通過程に於いて一旦お客様やお取引先からお預かりしているものですので本来なら負担は当然ともいうべきものですが、1年間の累積を納めるというのはなかなか大変な事です。
消費税は流通過程に於いて一旦お客様やお取引先からお預かりしているものですので本来なら負担は当然ともいうべきものですが、1年間の累積を納めるというのはなかなか大変な事です。
消費税対策のために会社設立しようという方は多いのですが、その節税とは具体的にどういったことなのでしょうか
個人事業主の消費税は課税売り上げ高が1000万円を超える場合は一律に支払義務が生じますが、個人事業を2年営み、3年目に法人にした場合はかなりの節税が可能です。?
仕組みとしては、個人事業の基準期間をうまく利用するということです。
確定申告の時期がせまってくると、個人事業から法人成りへの税金のご相談が多くなってきます。
中でも「消費税」のことについては、法人になった場合のメリットが大変大きいので、そのメリットをお伝えしたいと思います。
まず消費税とはそもそも何かを再確認しましょう。
消費税とは、商品やサービスの購入者である消費者が負担し、それらの提供を行った事業者が納税する間接税(税金を負担する人と、税金を納める人がちがうという仕組みの税金)です。売上により受け取った消費税額から仕入等により支払った消費税額を控除して事業者の納付税額を算出します。これは、商品やサービスの流通過程においての税の累積を排除するためです。